徳川直人、2006、『G・H・ミードの社会理論: 再帰的な市民実践に向けて』、東北大学出版会。
ここは、徳川直人の、社会学研究の、いわゆる公式サイトの、これはなに?(作品紹介)の、
G=H=ミードの社会理論
本・単著: 『G.H.ミードの社会理論: 再帰的な市民実践に向けて』
■ 書誌情報
■ English
■ 東北大学出版会
概要
「声と耳」を豊かに保つ社会認識につきそう社会学を再構想することはできないか。
高度な「情報社会」にもかかわらず私たちは「聞く耳を持つ社会」に生きていると感じることができていない。発話は単純なラベリングにおびえながらのものとなり、声もすぼんでしまう。そんな中、社会学を、読書会やフィールドワークを、「再帰的な市民の実践」として捉え直したい。プラグマティズムの哲学者、G.H.ミードの議論は、そのヒントに満ちている。ただし、そのためには、今日的な相互行為論およびフィールドワーク論とミードとの接続を、従来のシンボリック相互行為論との接続とは異なったかたちで、修復する必要がある。
ーー課題意識としては、内田義彦が構想した『社会認識の歩み』、すなわち社会思想の歩みと、一人一人の社会認識の歩みとを重ね合わせること、個々の社会認識に付き添う社会科学の構想、の再建、というものがありました。
ミードはどこにいたのか
ミード理論はいわゆる「子どもの社会化論」ではない。
--原典解釈作業としては、そこに私の強調点があります。 端的に言えば、かれの議論は第一次集団論ではなく、二次的構成活動における倫理についての考察だ、と読んだのです。
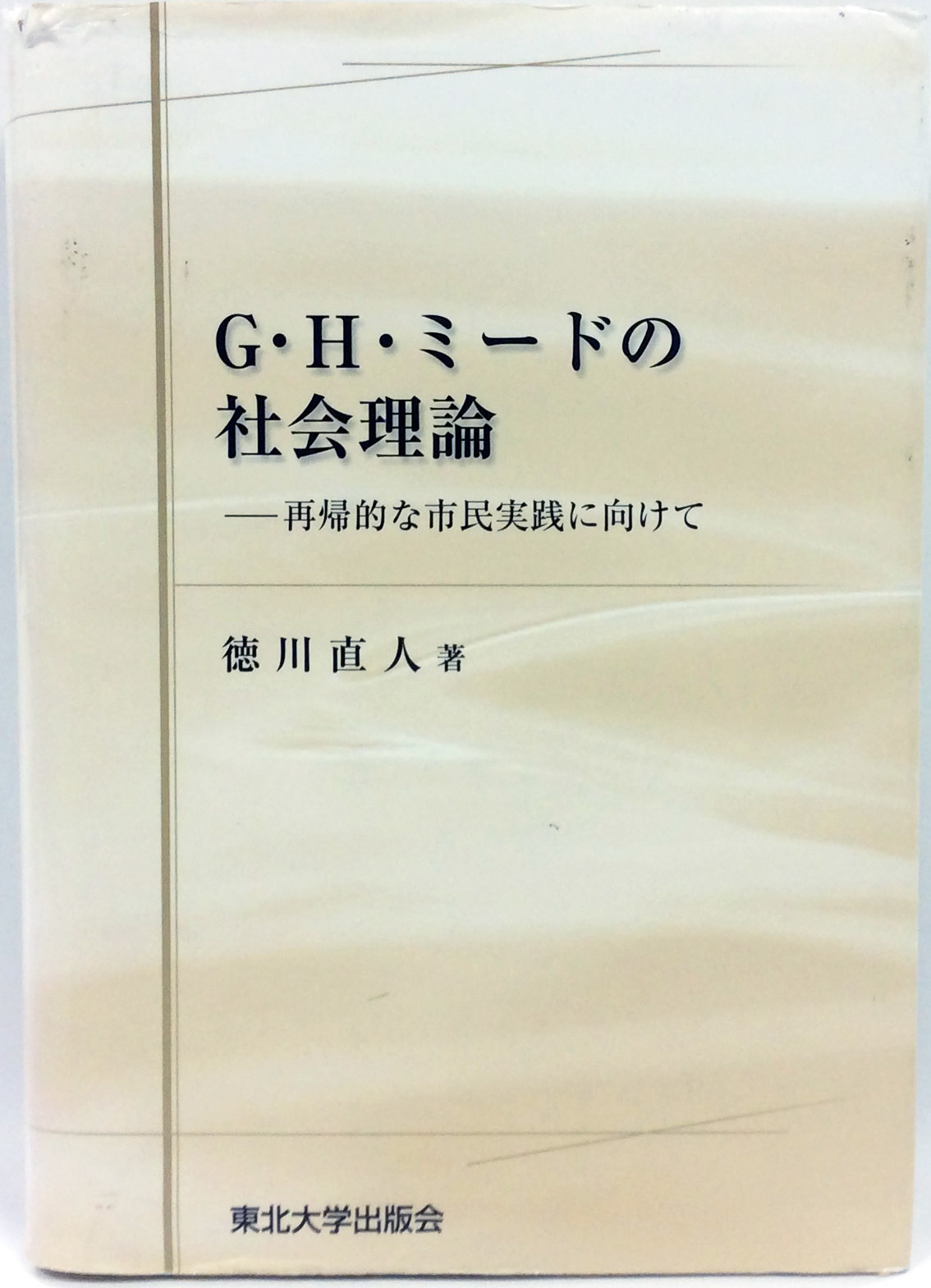
本書の発表は2006年(ですから書いていたのはその数年前)。ハンス=ヨアス、マリー=ジョ=ディーガン、ガリー=クックらによって、1980年代から90年代にかけ、めざましくミード研究が進展した後を受けてのことでした。
彼らの斬新な解釈の背後には、ミード直筆の論文、学術論文とは区別される時事的な論考、その思想形成過程、シカゴにおける活動史などについての貴重な資料発掘が含まれていました。没後に編纂・出版された書物に大きく頼っていた従来の研究に比すると、水準を飛躍的に向上させたもので、各自の課題関心や文脈による力点の違いや解釈のちがいはあれ、もうそれ以前に戻ることが認められなくなるほどの、画期的なものでした。
本書もですからミードの原典についてのテキストクリティークから始めなければなりませんでした。それまで「代表作」とされてきた『精神・自我・社会』(講義録とされているけれども速記録そのものではなく編集されている版)だけに頼ることなく、その講義録そのもの、他のミード自身が書いた学術論文、教育雑誌の編集者としての論考、市民委員会での報告やクラブでの講演、シカゴ大学図書館に収められている「ミードペーパーズ」に含まれている重要なメモや手紙、などを参照しました。(全部ではなく大きく限界はありますが)。
そうして、本書はミードを次の三つの角度から読みました。1)現代社会、とりわけ日本の今日の社会理論状況とミード、2)当時のアメリカにおける社会学や心理学とミード、3)革新主義から大戦を経て福祉国家と帝国主義が重なりあうアメリカ史の中のミード。
その検討の結果はおよそ次のようでした。
ジョージ・H・ミードは、「身振り会話」を端緒とする社会心理学によって精神・自我・理性といった啓蒙の課題をつくりかえ、市民たちの学習活動を基礎づけようと試みた思想家だった。その論の中心は「再帰」(鏡映・反射)の論理である。――それはあるいはごく標準的なミード像かもしれませんが、見知っていたはずのものごとが模索のあとになってみると新たな意味で浮かび上がってくる、といったことがあります。その意味とはーー
ミードは、革新主義時代を先導しつつ、a: 本質的な人間観や人間の本性論、あるいはモーレスや習慣を強調する社会哲学が文化的保守主義に陥っていること、b: 対象世界との関係性を抜きにした二者対話モデルの教育学や道徳が、知の一方的な伝達や教え込み、ひいては知の独占を暗示していること、c: 目的論的な社会進化思想、とりわけ改革ダーウィニズムの歴史主義、社会有機体思想に持ち込まれた心身二元論などが、テクノクラシーのディストピアに至り着きかねないこと、などと対峙していた。1910年前後に展開された社会心理学は、これらの問題への彼なりの解であり、本能説と模倣説、精神と身体、合理論と経験論などの対立に対する止揚でもあった。
ところが、戦時体制を契機に、革新主義的言説がおさまる枠組みに転換が生じた。ミードは1920年代に自我の発生、パースペクティブの客観的実在などについての社会理論を再展開し、d: 外集団に対する敵対や他者に対するラベリングを通した内集団の凝集という社会心理学的機序や、e: 社会コントロールへの national soul の動員が社会的自己を狭隘な愛国主義へと水路付け、それを通じて福祉国家が個々の生に対する計画と監視をおこないうる管理国家・軍事国家として出現しかねないこと、と向かい合っていった。
身振り会話と再帰の論理は、この福祉国家パターナリズムとの対峙という文脈のなかに位置づけ直された。
(本書i頁参照)。
再帰的な市民の実践としてのフィールド・ワーク
社会生活やそこでの経験について、語ったり聞いたりすること、書いたり読んだりすること。社会学者がおこなっているインタビューやフィールドワークは、その率先的・自覚的な実践です。
それは、経験をいかにして言葉にするのか、それをいかに解釈するのか、という、ミードの「身振り会話」の今日的なカウンターパートでしょう。
こうして、ミードの理論から私たちが今日うけつぐべき最も大きな遺産のひとつは「声と耳の身ぶり会話」です。ジョン・デューイも『公衆とその問題』の中で、「目は見物人だか耳は参加者だ」と述べました。これをフィールド・ワーク論と重ねて、その市民社会的意義を、強調したいと私は考えたのです。(本書末尾の「再叙述」)。
「ここから浮上するのは、対象を持つという課題、それについて聞く、話す、読む、書くといった営為の再建という課題である。それについての考察には、現今「表象の危機」と呼ばれている論点がかかわろう」(同上、337頁)。
「インタビューやフィールドワークを再帰的な市民の実践として理解する……[略]……「聞く」「書く」といった営為において「私は」何をどうしているのかと問いただす感受性を働かせてみるべきことを、 それは含意している」(本書、339頁)。
広告より--①
語り、聞く。声と耳を学びの契機に。ミード研究に内在してきた著者の斬新な再解釈。A5判、412頁、定価4200円(税込) (東北大学出版会の『河北新報』2006年11月21日付け広告)
広告より--②
種々の単純な話が流布する昨今、「声と耳」を豊かに保ち社会認識につきそう社会学を再構想することはできないか。古典と現在との間で「私」にできることは何か。本書は、ミード研究に内在してきた著者が、原典と史料をいっそう丹念に読むと同時に、シンボリック相互行為論と読書会の論理との接合をはかった研究書である。(東北大学出版会)
目次
概要と構成 凡例
はじめに 「身ぶり会話」考
第1部 自然・社会・自己
- 序章 統合と連帯
- 第1章 パースペクティブの重層としての自然
- 第2章 生命活動の過程としての社会
- 第3章 対話としての思考
- 第4章 歴史としての自己
第2部 ミードとアメリカ社会学・心理学
- 序章 実証主義と社会進化論
- 第1章 ミードとアメリカ社会学
- 第2章 計算と習慣
- 第3章 行動主義心理学
- 第4章 機能主義心理学
- 第5章 模倣と本能
- 第6章 社会心理学
- 第7章 「最初の本」構想
第3部 ミードとアメリカ社会
- 序章 「科学の方法」
- 第1章 「社会主義」とミード
- 第2章 セツルメントとシティ・クラブ
- 第3章 新教育と産業民主主義
- 第4章 労使紛争とミード
- 第5章 大戦とミード
- 第6章 差異と共同
むすび 再叙述
書評
- 吉原直樹先生:『宙(おおぞら)』(東北大学出版会会報)第20号(2007.6月刊)
- 宝月誠先生:『社会学研究』(東北社会学研究会)82号:147-153頁。(2007年10月刊)
- 伊奈正人先生:(ご自身のブログにて感想を公表していただきました)。
- 小川英司先生:『社会学評論』(日本社会学会)231号:388-9頁。(2007年12月刊)